2024.07.24
【メディア出演】日本の食文化を体感するメディア「SHUN GATE」に掲載いただきました
海を見る。
魚を知る。
たくさん生きている。
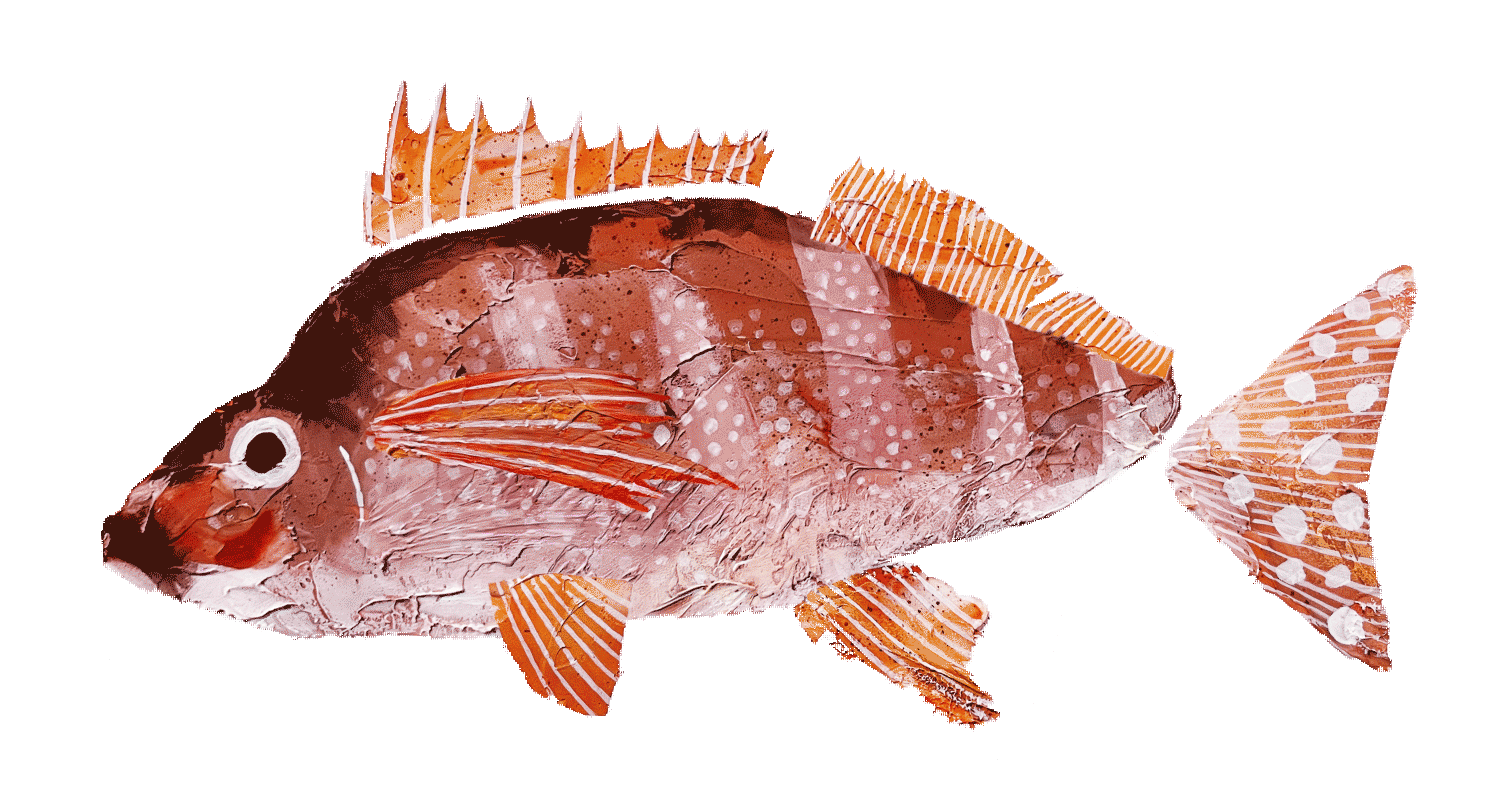
熱海の海は、千の魚の海。
人気のある魚だけが特別じゃない。
海の恵みは、もっと豊かで広くて深いはずだから。
海とつながるこの場所から、
海を知ろう。考えよう。食べよう。
人と同じように、たくさんの魚も、海も、
生きている。
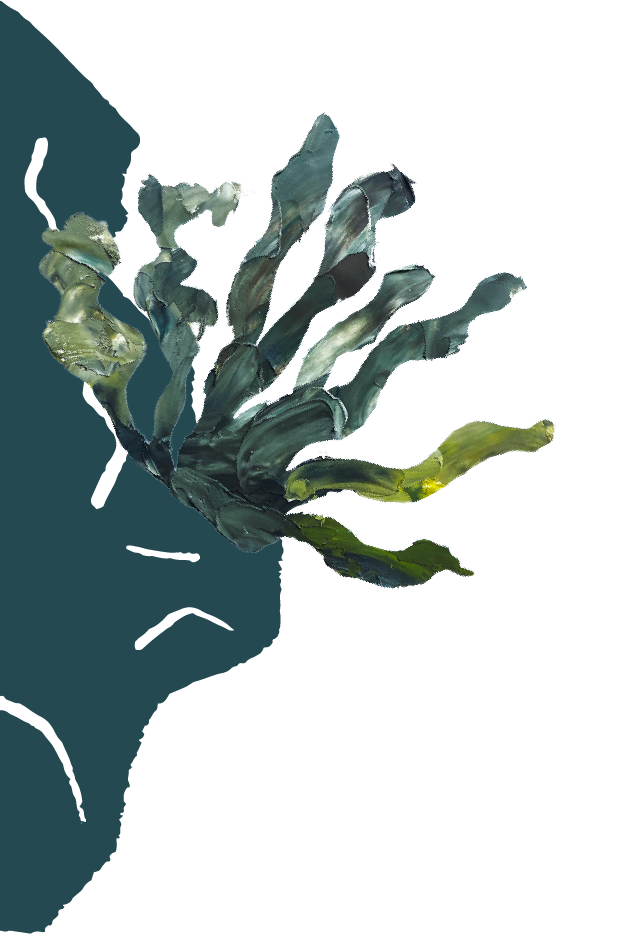




All→
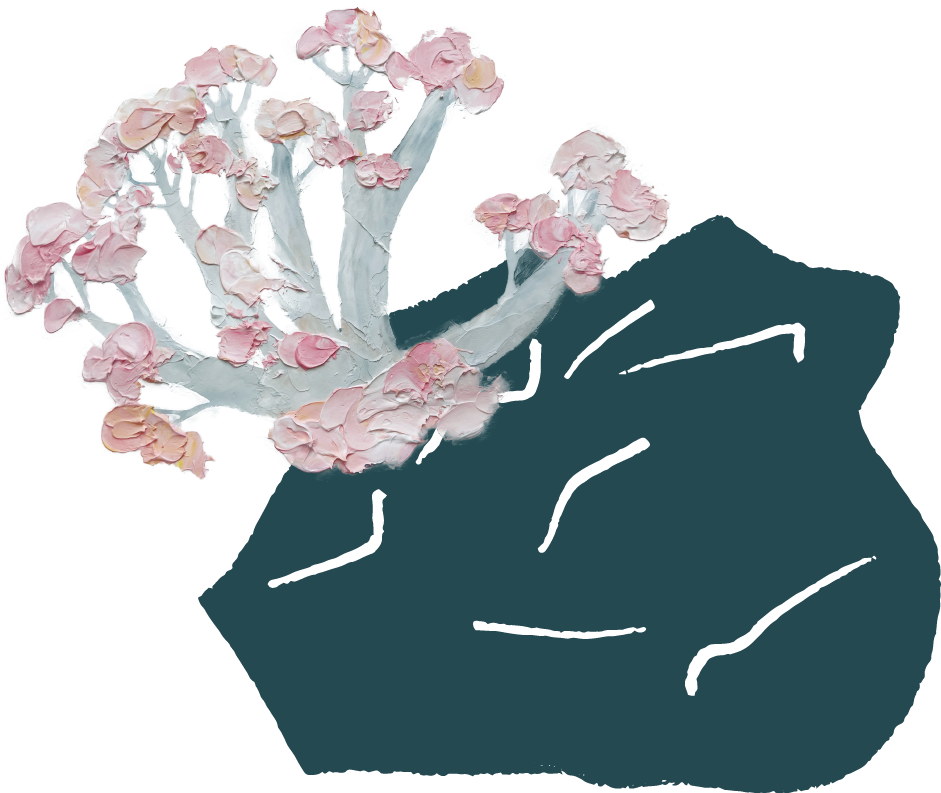
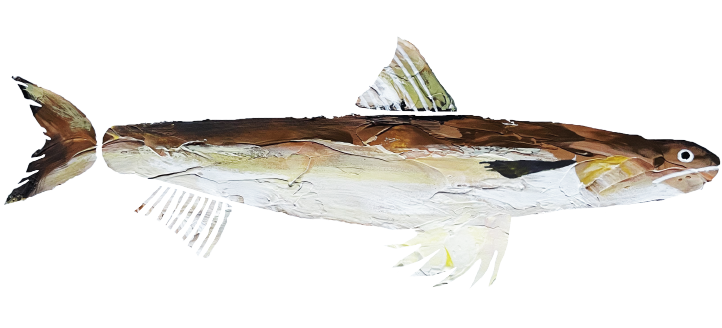
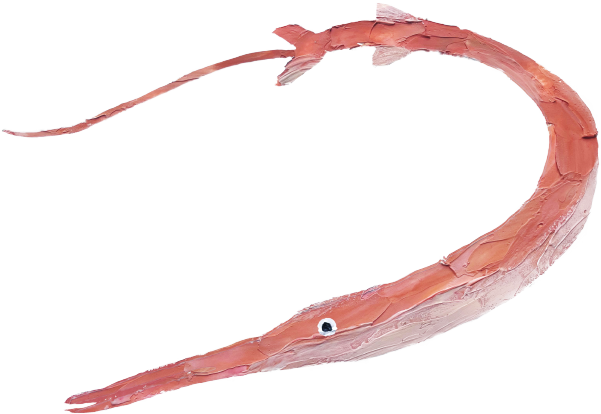
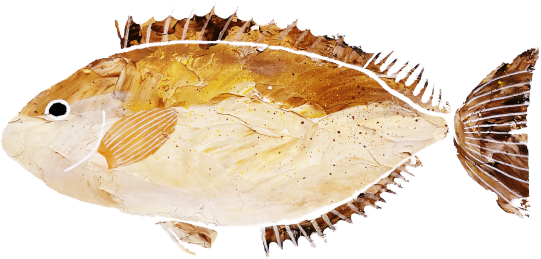
熱海千魚ベースは、3つの活動を軸に、
海への興味関心や理解を深める
「拠点(ベース)」作りに取り組んでいます。



